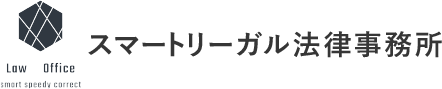2024/12/16 交通事故
交通事故の後遺障害14級とは?認定例と受け取れる賠償金の目安
交通事故によるケガが完治せず、一定の後遺症が残った場合には、「後遺障害」として認定される可能性があります。その中で「14級」は、後遺障害等級の中でも最も軽い等級とされていますが、それでも日常生活や仕事に影響を及ぼす場合があります。この記事では、後遺障害14級の基準や認定例、受け取れる賠償金の目安について詳しく解説します。

後遺障害14級とは?
後遺障害は、交通事故により生じた後遺症を等級ごとに分けた制度で、1級から14級までがあります。14級は、以下のような症状が対象です:
- 神経系の機能や運動能力の軽度な障害
- 日常生活で支障を感じる程度の障害
交通事故の後遺障害とは?種類と認定基準を徹底解説!
後遺障害14級の認定基準
交通事故後、日常生活や仕事に支障をきたすような後遺症が残った場合、医学的な根拠に基づいて後遺障害14級として認定される可能性があります。この等級は比較的軽い障害に該当しますが、症状が残ることで精神的・身体的な負担が継続するケースが少なくありません。以下に、14級の代表的な認定例とその具体的な内容を詳しく解説します。
1. 外傷性頚部症候群(むち打ち症)
交通事故で特に多いのが「むち打ち症」です。これは、追突事故や衝突事故の際に首が激しく揺さぶられ、筋肉や神経にダメージが生じることで起こります。14級に認定される場合としては、以下のようなケースが挙げられます:
- 首、肩、指先等に慢性的な痛みやしびれが残る
数か月以上治療を続けても、完全に痛みが取れず、日常的に違和感や不快感を感じる状態が該当します。 - 画像検査で異常が確認できる場合
MRIやCTで異常所見がみられる場合は認定されやすい傾向にあります。 - 日常生活に支障をきたす例
頭痛や肩こりが慢性的になり、デスクワークや家事に集中できない状況が続く場合
2. 視力や聴力の軽度な低下
視覚や聴覚の障害も後遺障害14級に該当することがあります。これらは、事故の衝撃や直接的な外傷によって生じることが多く、以下のような条件が認定の基準となります。
- 片耳の聴力が低下
会話をする際に音が聞き取りづらい、片方の耳だけで日常生活に支障が出る場合に認定されることがあります。 - 日常生活への影響
書類を読む際に目が疲れやすくなる、会議や電話対応で聴き返すことが増えるなどの実生活での困難さが認定に影響します。
3. その他の例
後遺障害14級には、他にも以下のような症状が該当することがあります:
- 指の動きが若干制限されている
事故による骨折や打撲の後遺症で、指を完全に曲げられない、または伸ばせない状態。例えば、ペンを持つ動作やキーボードのタイピングに支障があるケースが挙げられます。 - 交通事故後に歯を3本以上失った場合
外傷により歯が抜けたり、損傷して差し歯やインプラントが必要になった場合が該当します。特に前歯の場合は、見た目や食事への影響が大き - 軽度な皮膚の変形や傷跡
外傷や手術痕によって皮膚に軽い変形や傷跡が残った場合も、14級として認定されることがあります。これは特に顔や露出部に残った場合に影響が大きいです。
後遺障害14級の認定を受けるための手続き
1. 症状固定
治療を続けてもこれ以上改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。この段階で後遺障害診断書を作成してもらいます。
2. 後遺障害診断書の作成
医師に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。診断書には、具体的な症状やその影響について詳しく記載していただきます。
3. 後遺障害等級認定の申請
保険会社を通じて申請する方法(事前認定)と、被害者自ら申請する方法(被害者請求)があります。
後遺障害14級で受け取ることのできる賠償金の目安
後遺障害14級に認定されると、通院慰謝料や休業損害とは別に、主に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の2つを中心に賠償金を請求できます。これらは被害者の精神的苦痛や将来的な収入減少を補うためのものです。それぞれの項目について詳しく解説します。
1. 慰謝料
後遺障害14級に該当する場合、被害者が事故により被った精神的苦痛に対する補償として慰謝料が支払われます。支払い金額は基準によって異なりますが、以下のような目安があります:
- 裁判基準
裁判基準では、後遺障害14級に対する後遺障害慰謝料は110万円とされています。 - 自賠責保険基準
自賠責保険から支払われる後遺障害14級の支払額は一律75万円と決まっています。 - 任意保険基準
保険会社は、何も言わず後遺障害慰謝料75万円を提示してくることが一般的です。
注意点:
慰謝料の金額は、事故の具体的な状況や交渉の方法によって大きく変わるため、適切な基準で請求することが重要です。弁護士に相談することで、裁判基準に近い賠償額を得られる可能性が高まります。
2. 逸失利益
後遺障害14級は、労働能力に一定の支障をきたすとみなされるため、将来的な収入減少を補うための逸失利益を請求できます。逸失利益の算出には以下の要素が用いられます:
計算方法
逸失利益は以下の計算式で求められます:
年収 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- 年収
被害者が事故前に得ていた年収が基準となります。専業主婦の方、収入が不明確な方の場合は、平均賃金や統計データが使用されることもあります。 - 労働能力喪失率
14級では、労働能力喪失率が5%とされています。これは、事故により労働能力が5%低下したとみなされることを意味します。 - 就労可能年数
原則、事故発生時点から67歳までが就労可能年数とされます。ただし、5年や10年に制限されるケースもあり、個別に計算が必要です。 - ライプニッツ係数
将来の収入を現在価値に割り引くための係数です。就労可能年数に応じた係数が使用されます。例えば、10年間の場合は7.7217を使用します。
具体例:
年収400万円の方が、10年間の逸失利益を請求する場合、計算は次のようになります:
400万円 × 5% × 7.7217 = 約154万円
この金額が、労働能力喪失による将来的な収入減少分として請求可能です。
注意点:
逸失利益を適正に算出するには、特に源泉徴収票、給与明細、納税証明書、確定申告書など収入に関する明確な根拠が必要です。保険会社が低額な提示をしてくることもあるため、弁護士に依頼して正当な金額を算出・請求することをお勧めします。
実際の賠償金額を高めるためのポイント
- 医師の作成した診断書・意見書の準備
医師による後遺障害診断書や意見書などが、慰謝料や逸失利益の請求において重要な証拠となります。症状やその影響を詳細に記載してもらいましょう。 - 適切な交渉の実施
保険会社は低額な提示をしてくることが多いため、専門知識を持つ弁護士を介して交渉を行うことで、賠償金額を引き上げることが可能です。 - 裁判基準を意識する
賠償金を裁判基準で請求する場合、交渉が難航することもありますが、最終的には裁判所の基準に基づいた適正な金額を得られる可能性があります。
後遺障害14級が認定されるポイント
後遺障害14級の認定を受けるには、適切な診断と証拠の提示が鍵となります。この級は比較的軽度とされるものの、日常生活に支障をきたしていることを正確に示すことが認定への大きなステップとなります。以下に、重要なポイントを詳しく解説します。
1. 医師の診断が最重要
医師による後遺障害診断書は、後遺障害認定の基盤となる重要な書類です。適切な診断を受けるためには、以下の点に注意してください:
- 症状を具体的に伝える
痛みやしびれの部位、頻度、強さ、生活への影響を詳細に説明します。「なんとなく痛い」といった曖昧な表現ではなく、以下のように具体化することが大切です:- 「朝起きたときから常時首から肩にかけて痛みがあり、家事を始めるのに時間がかかる」
- 「長時間のデスクワーク中に手のしびれの影響で、仕事効率が下がる」
- 専門的な検査を依頼
MRIやCTなどの画像検査で異常が見られない場合でも、神経学的検査や整形外科的検査によって、症状を補強する証拠を得ることが可能です。 - 診断書の記載内容を確認
診断書には「症状の継続性」「日常生活への影響」などの記載が求められます。症状が慢性化している点や日常生活で支障をきたしている点が明確に記載されているか確認しましょう。
2. 普段の生活での影響を記録する
事故後の生活がどのように変化したかを記録し、それを医師や認定機関に伝えることが重要です。これにより、事故による後遺障害が日常生活に与える具体的な影響を証明できます。
むち打ち症の場合の具体例
むち打ち症(外傷性頚部症候群)は、後遺障害14級で最も多いケースの一つです。この症状が認定されるには、以下のような影響を正確に伝える必要があります:
- 痛みやしびれが日常的に続く
「家事や育児中に肩や首に激しい痛みを感じる。家事を配偶者に替わってもらっている」「趣味だったスポーツを完全に断念した」といった影響を明確にすることで、生活の質が低下したことを示します。 - 天気や気圧の変化で症状が悪化する
「雨の日や台風の接近時に痛みが増し、外出できない」などの具体的なエピソードが有効です。 - 仕事への支障
デスクワーク中に集中力が続かない、運転中に首を動かすのがつらいなど、仕事の効率や安全性に影響を及ぼすエピソードも伝えましょう。
3. 症状を医師に正確に伝え、診断書に反映してもらう
医師に伝える際のポイントとして、「症状の詳細」と「日常生活への影響」を過不足なく説明することが重要です。また、口頭で伝えるだけでなく、症状日記や写真記録を用いることで客観性を高められます。
症状日記の作成方法
- 書く内容
- 痛みやしびれの程度(例:「10段階で7」)
- 特に症状が悪化するとき(例:「雨の日」「長時間の作業後」)
- 症状が原因でできなかったこと(例:「家事ができない」「子供と遊べない」)
- 活用例
症状日記を医師に見せることで、診断書の内容を補完する材料として使えます。また、認定機関に提出する際にも、客観的な証拠として役立ちます。
4. 認定機関への提出資料を整える
認定機関は、提出された資料を基に後遺障害の有無を判断します。そのため、診断書や症状日記以外にも、次のような資料を準備しましょう:
- 医療費の明細や通院記録
- MRIやCT検査結果(異常がない場合も含む)
- 事故当時の警察の報告書
まとめ
後遺障害14級は「軽い障害」とみなされることが多いですが、それでも日常生活や仕事に影響を与える可能性があります。認定を受けることで、適切な賠償金を受け取る権利が発生します。
もし交通事故で後遺障害14級に該当する可能性がある場合は、弁護士への相談を検討しましょう。「スマートリーガル法律事務所」では、交通事故の後遺障害認定に関するご相談を受け付けております。豊見城市内など近傍の場合は訪問相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。