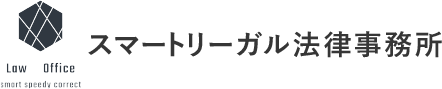相続トラブルの解決までの流れ
相続トラブルの解決までの流れ
相続に関するトラブル(遺産分割・遺言無効・遺留分侵害など)の解決に向けた、弁護士のサポートの流れをご説明します。
1. ご相談・方針決定
まず、初回のご相談の中で以下の内容を確認します。
✅ 相続の基本状況とトラブルの内容
・被相続人の死亡日、相続人の範囲と人数、戸籍の確認
・遺言書の有無(公正証書・自筆・口頭など)
・遺産の内容(不動産・預金・株式・負債など)登記簿謄本、名寄帳、通帳等
・現在の話し合い状況と他の相続人の態度
✅ ご希望と解決方針の確認
・一定程度譲歩した円満な分割を望むか、正当な取り分の確保を重視するか
・調停を避けたいか、訴訟も視野に入れるか
・弁護士が代理人として交渉に入るかどうか
✅ 弁護士費用のご説明
・着手金(案件受任時。交渉、調停、訴訟ごとに発生します。)
・成功報酬(遺産の取得に応じて)
・実費(戸籍・登記簿の取得費用、調停申立費用など)
2. 委任契約の締結
正式にご依頼いただく場合、弁護士との間で「委任契約書」を締結します。
今後の手続きの進め方・費用・連絡方法などを明確にします。
3. 調査・証拠収集
相続関係や財産内容を明確にするため、弁護士が必要な調査を行います。
📌 主な調査内容
✅ 相続関係説明図の作成(戸籍・除籍の取り寄せ)・法定相続情報一覧図作成(法務局)
✅ 財産調査(預金残高、不動産、株式など。登記簿、固定資産評価証明書)
✅ 遺言書の有効性調査(筆跡鑑定や作成経緯の確認)
✅ 生前贈与・使途不明金の確認
4. 内容証明による請求・交渉の開始
相続人の一部に対して、遺産分割協議の申入れや遺留分侵害額請求を、内容証明郵便で送付することがあります。
📌 内容証明に記載する内容
✅ 請求の趣旨(遺産分割協議への参加/遺留分侵害の返還請求など)
✅ 回答期限(通常2週間〜1か月)
✅ 応じない場合には家庭裁判所への調停申立を検討する旨の記載
5. 示談交渉(協議)
他の相続人と交渉し、遺産分割の内容について合意を目指します。
この段階で合意に至れば、「遺産分割協議書」を作成し、円満解決となります。
✅ 協議書のポイント
✔ 各相続人が取得する財産の内容
✔ 代償金の有無・支払期限・方法
✔ 公正証書化することで後日のトラブルを防止
✔ 登記・名義変更の段取りまでサポート可能
💡 示談のメリット
✔ 手続きが早く終わる
✔ 裁判に比べて費用・精神的負担が少ない
✔ 柔軟な分割内容の合意が可能
6. 家庭裁判所での調停・審判(協議が不成立の場合)
遺産分割に関して協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停(遺産分割調停や遺留分侵害額請求調停など)を申し立てます。
✅ 調停の流れ
① 調停申立書の作成・提出
② 裁判所での期日(通常1〜2か月に1回)
③ 話し合いが不成立の場合、審判に移行
④ 審判により裁判所が分割方法を決定
📌 注意点
・調停・審判には半年〜1年程度かかる場合がある
・不動産評価、遺産目録の作成など専門的な準備が必要
・相手が応じない場合でも強制力のある解決が可能
7. 遺産の取得・手続き完了
✔ 示談または調停・審判で取得が決まった遺産の受け取りを確認
✔ 不動産の名義変更、預貯金の解約手続き等もサポート可能
✔ 相手方が代償金などの支払いを拒んだ場合は強制執行も検討
8. その後の対応
✔ ご希望に応じて相続税の専門家(税理士)をご紹介
✔ 不動産の売却や遺品整理、相続登記の実務サポート
✔ 家族間トラブルの再発防止のためのアドバイス